生成AIイラストと著作権|なぜ気をつけなきゃいけないの?
生成AIでイラスト作成が誰でもできる時代だからこそ著作権を気にしよう
最近では、誰でも簡単にAIでイラストを作れるようになりました。特にMidjourneyやDALL·E、Canvaなどの画像生成ツールは、プロ並みの絵を数秒で出力してくれます。
しかし、「自分でプロンプトを入力して作った画像だから自由に使っていい」とは限りません。実は、生成されたイラストには著作権が発生しないケースも多く、逆にトラブルの原因になることもあるのです。
トラブルを防ぐために、まず生成AIと著作権の基本を知ろう
AIイラストを安心して使うには、著作権の仕組みと生成AIにおける特有の注意点を知っておく必要があります。
そもそも著作権って誰のために、何のためにあるの?
著作権とは簡単に言うと制作物に対する、模倣、引用、改変の権利について制限したルールです。
つまり、人が作ったコンテンツを勝手に利用することや改造して利用することへの制限します。著作権は特許と違い国をまたいで適用されるルールになるので、別の国で作られたコンテンツなら勝手に模倣して使っていいとはなりません。
著作権は「創作した人(クリエイター)」を守るための権利
著作権は、創作した本人の努力や創造性を守るために存在します。無断で真似されたり、商用利用されるのを防ぐための法律的な仕組みです。
創作者の保護により文化をもっと発展させようという狙いがあるのです。
創作が尊重されることで、新しい作品が生まれ続け、文化全体が豊かになっていきます。著作権は単なるルールではなく、「未来の創作」を守る基盤でもあるのです。
「使う側」のルールでもあり、創作を続けやすくするための仕組み
著作権は、使う側にとっても大事なルールです。正しく使うことで、自分も安心して創作活動ができるようになります。
著作権のおかげで自分の著作物を守る事を守り、さらには自分の作品を広めてもらう事につながります。
POINT: 守るべき理由 = クリエイターの未来を守るため + 自由に使うためにも必要!
生成AIイラストにおける著作権の基本
生成AIが作った画像は著作権が発生しにくい
AIが自動的に作った画像には、「人間の創作性がない」と判断され、著作権が認められないケースが多くあります。つまり、自分が作ったと思っていても、法律的には無権利状態になることもあります。
ただし、AIがどんなデータを学習しているかも重要です。著作権で保護された画像を無断で学習している場合、そのAIが出力する画像も著作権的に問題がある可能性があります。
ツールごとに利用規約が異なる(例:Midjourney、Canva、DALL·E)
AIツールごとに商用利用の可否や著作権の扱いは違います。たとえば、Midjourneyは有料会員のみ商用利用が可能、DALL·EはOpenAIのガイドラインに従う必要があります。
ガイドラインと聞くと小難しく感じますが、OpenAIのガイドラインは非常に読みやすく配慮されているガイドラインになってますので、個人利用以外で利用される方は必ず目を通しましょう。
OpenAIガイドラインはこちら
POINT: 使ったAIサービスごとにルールが違うので、事前に規約をチェック!
実際に起きた著作権問題とその結果
事例①「AIイラストがコンテスト受賞→取り消し」
問題: Midjourneyで作成されたイラストが美術コンテストで入賞。しかし後に「人間の創作性が不足している」として受賞が取り消されました。
ポイント: AIが出力しただけの画像は、人の手が加わっていない場合「著作物」として認められにくいことを示す事例です。
事例②「有名絵師の絵柄を学習したAIモデル問題」
問題: 特定の有名イラストレーターの作品を無断で学習したAIモデルが、絵柄を模倣した画像を大量生成。SNSやニュースで批判が集まりました。
ポイント: AIが学習する素材に著作権がある場合、それを元に出力された画像も法的・倫理的に問題が生じる可能性があります。
POINT: 「他人の成果を土台にしていないか?」を意識するのが大切!
生成AIイラストを使うときに守るべき3つのポイント
- 使用するAIツールの規約を必ず確認する
- 学習素材の著作権に問題がないか意識する
- 商用利用・二次利用が許可されているか確認する
1.使用するAIツールの規約を必ず確認する
利用規約を読まずに使うのはNG。商用利用できるのか、著作権は誰にあるのかなど、ツールごとの違いを理解しておきましょう。
2. 学習祖沿いの著作権に問題がないか意識する
可能であれば、AIが使っている学習データの出典や性質も確認しましょう。公的データやフリー素材で構成されているAIなら比較的安心です.
3.商用利用・二次利用が許可されているか確認する
ブログ・商品・広告などで使う場合は「商用利用OK」の明記があるかどうかが必須です。また、加工・再配布の可否も要確認です。
自分で創作性を加えることでリスクを減らす
AIが出力したものに、自分で構図を足したり編集を加えると、「創作性」が認められやすくなります。文章などでは必ず校正するようにして自分なりの言葉に変えるようにしましょう。
POINT: 守るべきこと = 自分の作品を守ることにつながる!
まとめ|自由に創作を楽しむために、ルールも一緒に覚えよう
「作る自由」と「守る責任」はセット
AIが発展しても、創作の価値やルールは変わりません。正しい知識を持つことが、より自由な創作を可能にします。
安心してイラスト活動を続けるために知識を持つことも重要です。トラブルに巻き込まれず、自分の作品を堂々と発表・活用できるようになるためにも、著作権の知識は武器になります。
次は「生成AIイラストの上手な使い方」記事へ
イラスト制作のテクニックやプロンプトの工夫を知りたい方は、次の記事で実践的な内容をご紹介しています!


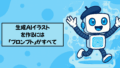
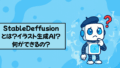
コメント