「生成AI」という言葉をよく耳にするけれど、実際どういうものなのか、なぜこんなに注目されているのか、そして私たちの生活や仕事にどう役立つのか—
そもそも「生成AIとは何か?」
生成AIとはなにか。そんな疑問にお答えします。この記事では、AIに詳しくない方でも理解できるよう、基本から実践的な活用法まで分かりやすく解説します。
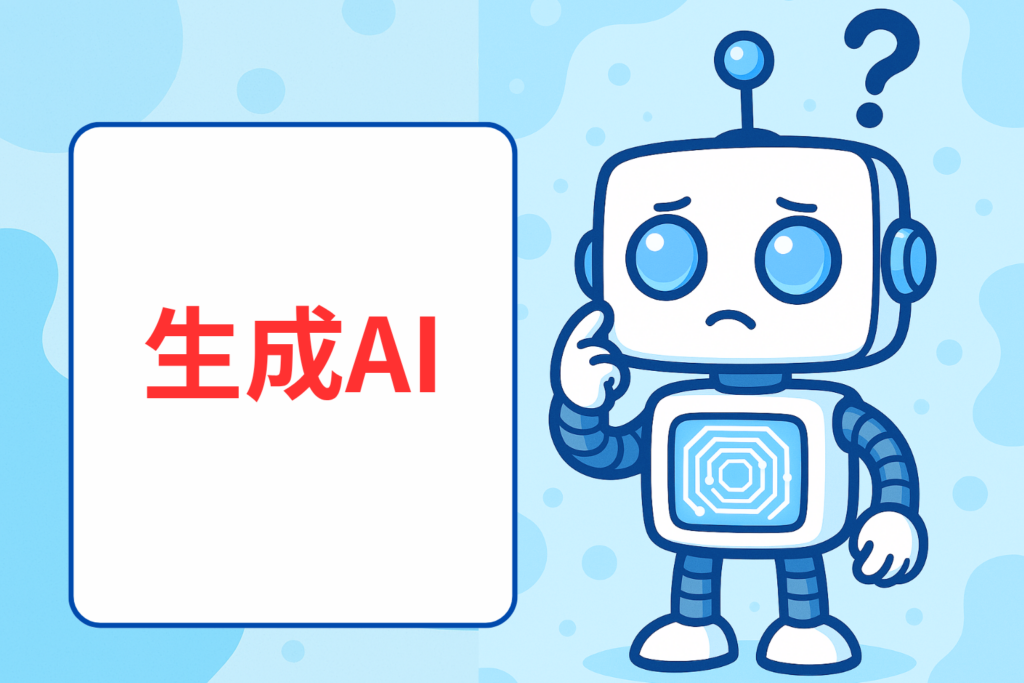
AIの中でも”作り出す”のが得意なタイプ
生成AI(Generative AI)とは、なにかというと人工知能(AI)の一種で、新しい作品を「生成」することに特化したものです。
従来のAIが「分析」や「判断」を得意としていたのに対し、生成AIは文章、画像、音声、プログラムコードなど、人間が作るような作品を自ら創り出すことができます。
たくさんのデータから学習し、そのパターンを理解した上で、まったく新しいものを作り出せるのが大きな特徴です。
例えば、数百万の文章から「自然な日本語の書き方」を学び、それを応用して新しい文章を書いたり、同じく数百万もの画像を見て「犬はどういう形をしているか」を理解し、指示に従って新しい犬の画像を描いたりできるのです。
生成AIとはなにか?例えるなら「アイデア職人AI」
職人が材料と技術を組み合わせて新しい作品を生み出すように、生成AIも学習したデータという「材料」と、生成のルール(アルゴリズム)という「技術」を使って新しい作品を作り出します。
人間が「こんな文章を書いて」「こんな画像を作って」といった指示を出しても、それを理解して形にしてくれる、まるで頭の中のイメージを具現化してくれる便利な相棒のような存在です。
普通のAI(分析・分類系)と生成AIの違いとはなにか?
従来の「普通のAI」と生成AIは別物で大きな違いがあります、それはその目的が違います。
従来のAI(分析・分類系)とはなにか?
- データを分析し、パターンを見つける
- 「Yes/No」の判断や予測をする
- 持っているデータの中から正解を選ぶ
- 例:スパムメール検出、顔認識、データ分析
生成AIとはなにか?
- 新しい作品を創造する
- 人間のような文章や画像を作り出す
- 指示に基づいて独自の正解を生み出す
- 例:ChatGPT、DALL-E、Midjourney
簡単に言えば、従来のAIが「判断係」なら、生成AIは「クリエイター」と言えるでしょう。
生成AIは、なぜ今こんなに話題になってるの?
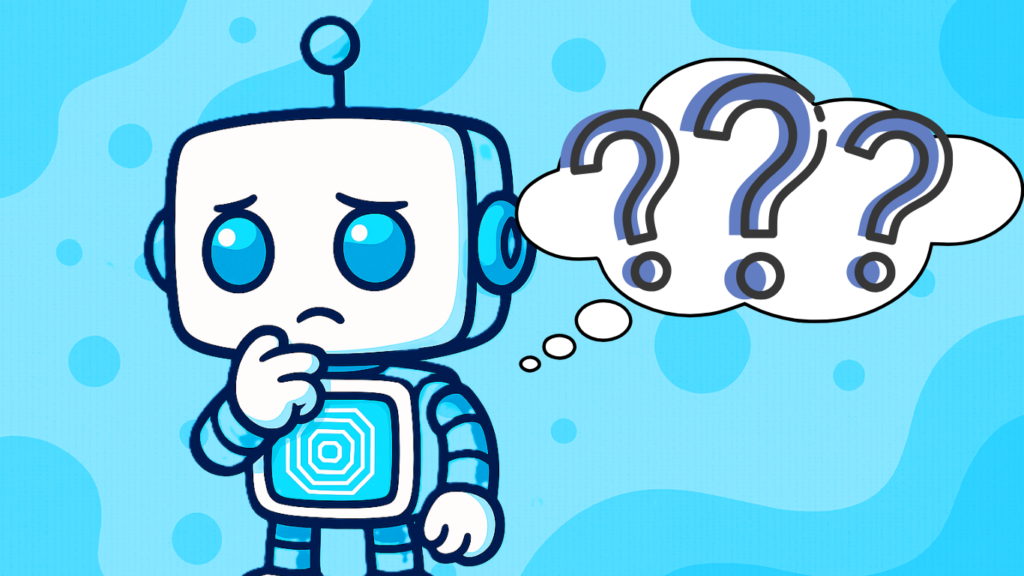
ChatGPTという「高精度、自然な対話、豊富なデータ」をもつAIの登場がきっかけ
生成AIが急速に注目を集めるようになった最大のきっかけは、2022年11月にOpenAIが公開した「ChatGPT」の登場です。
生成AIとは何かを知る上で「ChatGPT」がかなり大事になってきます。
それまでも生成AIの研究や開発は進んでいましたが、ChatGPTは一般の人々でも簡単に使える形で提供され、その高い精度と豊富なデータ、自然な対話能力に多くの人が驚きました。
わずか2か月で1億人のユーザーを獲得するというビックリするような広がりを見せ、AIを世界中の人々に対して身近にしたのです。
誰でも簡単に特別なスキルがなくても生成AIが使える時代に突入
生成AIが注目される理由のひとつに、その「使いやすさ」があります。以前のAI技術は専門知識がないと扱えないものが多く、一般の人々にとってはハードルが高い存在でした。
しかし、ChatGPTやMidjourneyといった現代の生成AIツールは、専門知識がなくても、普通の言葉で指示を出すだけで利用できます。
「プログラミングの知識は不要」「専門用語を覚える必要なし」というハードルの低さが、多くの人々にAIを身近なものとして感じさせています。
技術の進化が”目に見える”ようになったから
これまでのAI技術の進化は、専門家たちでしか操作できないため、一般の人々には見えにくいものでした。
しかし、生成AIの場合、その進化の成果が「テキストの生成」「画像の作成」「音声の変換」など、誰でも操作可能になり、体感できる形で表れています。
例えば、AIが書いた文章や画像に人らしさを感じるなど、その進化は見て分かります。技術の進歩を実感できることが、人々の関心を高める大きな要因となっています。
何ができるの?代表的な生成AIについて
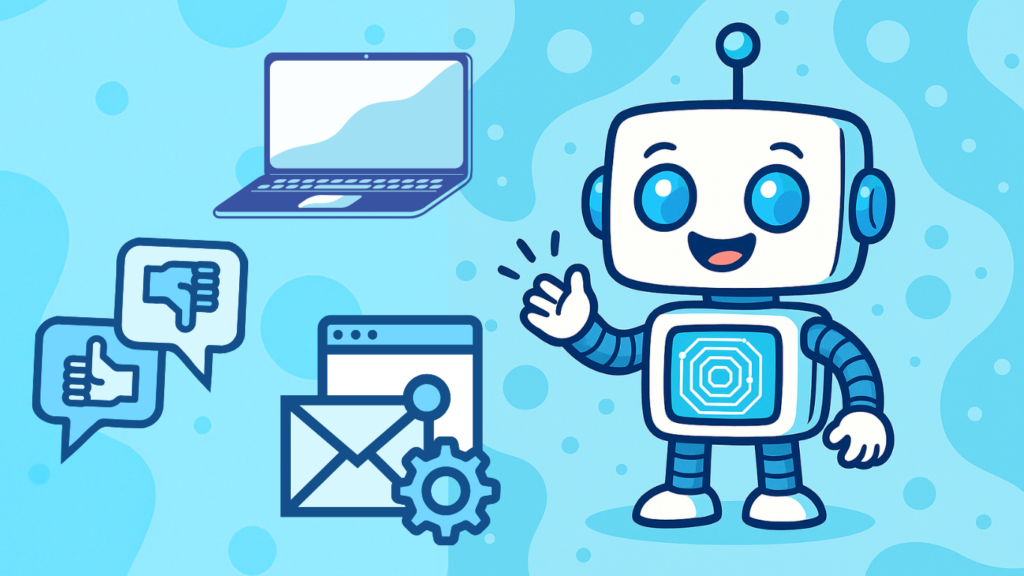
ChatGPTとはなにか(文章生成AI)
OpenAIが開発したChatGPTは、人間のように対話ができるAIとして広く知られています。
質問に答えるだけでなく、文章の作成、情報の要約、アイデア出し、翻訳、プログラミングコードの生成など、幅広いタスクをこなすことができます。
さらに、逆質問なども行ってくれて何を伝えればいいのかも教えてくれます。より高性能なGPT-4モデルを使用できるPlus版(月額$20)もありますが、無料版でも十分に活用できます。
ビジネスや学習、日常生活のさまざまな場面で文章作成の助けになるツールです。
Copilotとはなにか(仕事効率化AI)
Microsoftが提供する生成AI。Copilotは、Office製品(Word、Excel、PowerPointなど)と連携して働く生成AIです。
文書作成の手助け、データ分析、プレゼン資料の自動生成など、日常的なオフィスワークを効率化することができます。
例えば、「四半期の売上データをグラフにして、主なポイントをまとめたスライドを3枚作成して」といった指示を出すだけで、基本的な資料を自動生成してくれます。
個人的にはEdgeで検索した政府が発表した小難しいPDF資料を要約して分かりやすくし理解をするのに役立てています。
CanvaやMidjourneyとはなにか(画像・デザイン生成AI)
Canva AIは、人気のデザインツールCanvaに組み込まれた生成AI機能で、テキストプロンプトから画像を生成したり、デザインの自動提案を受けたりできます。
プロのデザイナーでなくても、クオリティの高いビジュアルコンテンツを簡単に作成できるのが魅力です。本ブログでも、ちょいちょいCANVAで生成したイラストを使っています。
そしてMidjourneyは、テキスト入力から高品質な画像を生成するAIで、そのアート性の高さで注目を集めています。「夕日に照らされた富士山と桜の木」といった指示から、まるでプロのアーティストが描いたような美しい画像を生成できます。
DeepSeeKとはなにか(情報探索に強い生成AI)
DeepSeeKは、大量の情報の中から必要なデータを探し出し、整理・要約する能力に長けた生成AIです。
ウェブ上の情報検索だけでなく、企業内の膨大なデータベースから必要な情報を探し出し、わかりやすく提示することができます。
特に複雑な質問や、多くの情報源を参照する必要がある場合に威力を発揮し、調査や研究作業の効率化に貢献します。
知っておくべきメリットと注意点
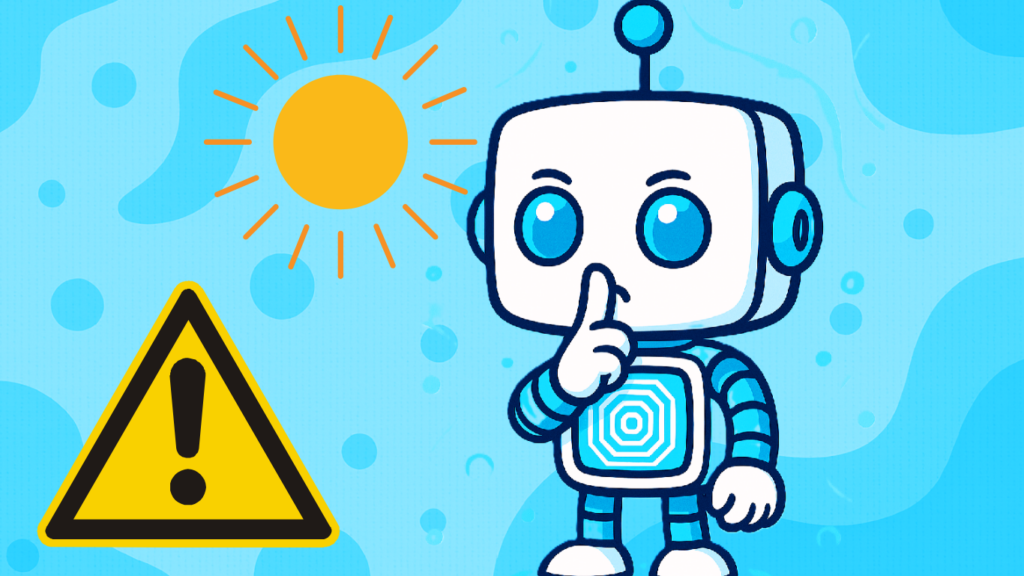
時短・効率化・アイデア補助がすごい
生成AIの最大のメリットは、時間の短縮と作業効率の向上です。
例えば
- 文章作成の下書きや校正を助けてくれる
- 複雑な情報をわかりやすく要約してくれる
- デザインのイメージを素早く作成できる
- プログラミングコードの基本部分を自動生成してくれる
また、アイデア出しのパートナーとしても優れています。
「このプロジェクトのネーミング案を10個考えて」「この商品のターゲット層を分析して」といった形で、発想の幅を広げる助けになります。
でも”完全に正しい”わけじゃない?
生成AIは非常に便利ですが、常に正確というわけではありません。
特に注意すべき点として
- 「もっともらしい嘘」を言うことがある(AIハルシネーション)
- 2023年以降の最新情報には弱い(学習データの制限による)
- 複雑な数学や専門的な計算にミスが生じることがある-
文脈によっては不適切な回答をすることがあるそのため、特に重要な情報や専門的な内容については、必ず人間が確認する習慣をつけることが大切です。
著作権や情報の信頼性にも注意が必要
生成AIを使う際には、著作権や情報の信頼性にも注意が必要です
- AIが生成したコンテンツの著作権は国や状況によって扱いが異なる
- 企業の機密情報をAIに入力すると、情報漏洩のリスクがある
- AIが作成した内容をそのまま商用利用する場合の法的リスク
- 出典が明確でない情報は、別途確認が必要
特にビジネスでの利用においては、自社のAI利用ポリシーを確認し、適切な範囲で活用することが重要です。
とは言っても、このような事項に注意して活用すれば、多大な恩恵を得られるでしょう。
生成AIを今日から始めるなら?おすすめの使い方とは?
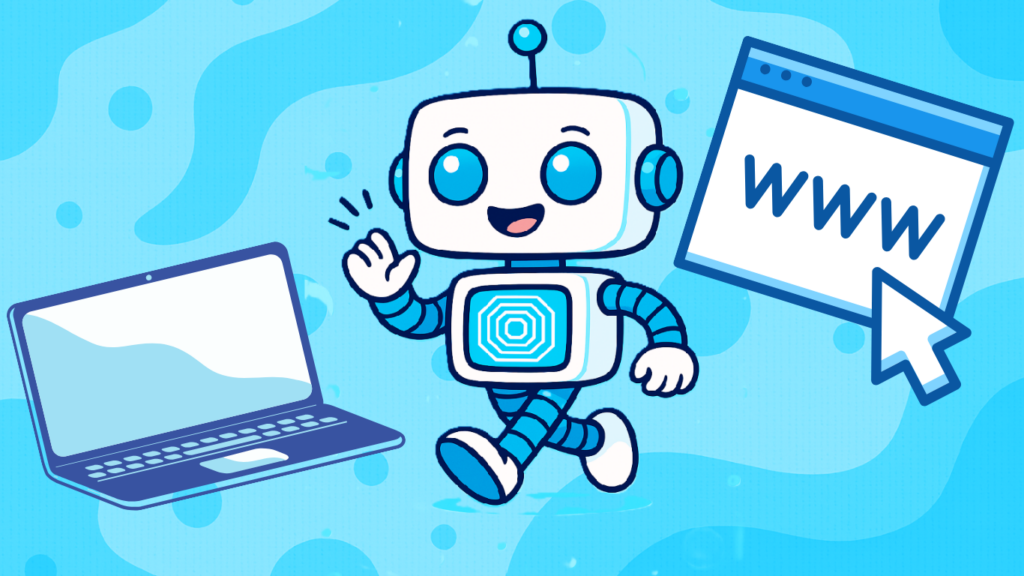
まずは生成AIはChatGPTで試してみよう(無料からOK)
生成AIを初めて使うなら、まずはChatGPTの無料版から始めるのがおすすめです。アカウント登録だけで利用でき、特別なスキルも必要ありません。
少しずつ複雑なタスクに挑戦する
初心者におすすめの簡単な使い方:
- ChatGPTにアクセスしてアカウントを作成 https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/
- 興味のあるトピックについて質問してみる
- 仕事や勉強に役立ちそうな簡単なタスクを頼んでみる
- 例:「このメールの返信文を考えて」
- 例:「この概念を小学生にもわかるように説明して」
仕事・副業・勉強…それぞれの活用例
ビジネスでの生成AI活用例:
- 会議の議事録から要点をまとめる
- プレゼン資料の構成案を考える
- 営業メールのテンプレートを作成する
- 社内マニュアルの初稿を作成する
副業・フリーランスでの生成AI活用例:
- ブログ記事のアイデア出し
- ウェブサイトの文章作成補助
- SNS投稿の文案作成
- クライアントへの提案書のブラッシュアップ
学習・研究での生成AI活用例:
- 難しい概念の解説を求める
- レポートの構成を考える
- 学習計画の立案を手伝ってもらう
- 論文の要約や参考文献リストの整理
生成AIの不安を減らすために”試してみる”がいちばんの近道
生成AIに対して「難しそう」「使いこなせるか不安」と感じる方も多いですが、実際に使ってみると意外と簡単だと感じることが多いです。最初は完璧を求めず、気軽に試してみることが大切です。
例えば:
- 「今日の夕食のレシピを考えて」
- 「次の休日におすすめの過ごし方は?」
- 「このニュース記事を3行で要約して」
こうした簡単なリクエストから始めて、徐々に複雑な依頼にステップアップしていくことで、自然と使いこなせるようになっていきます。
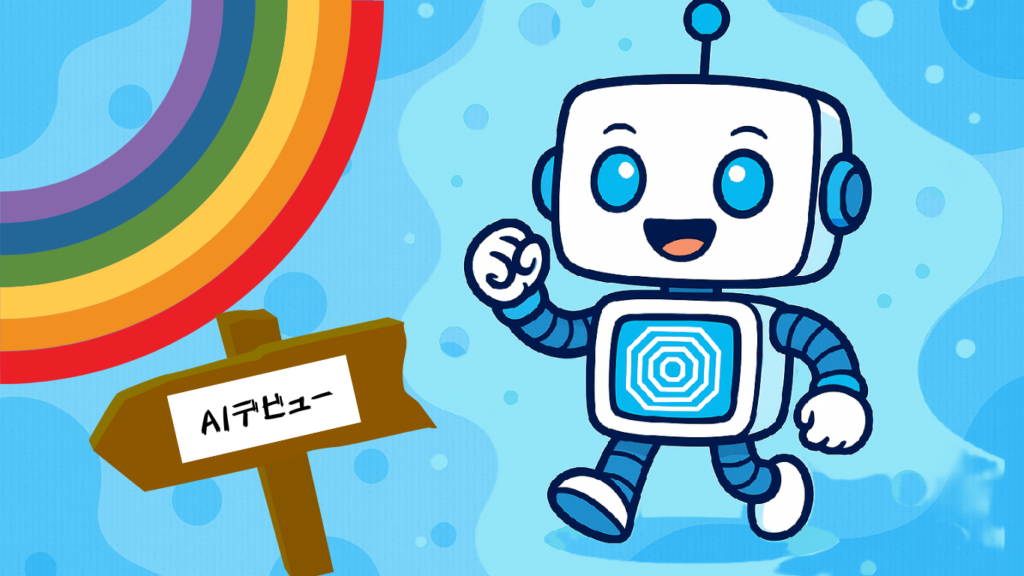
まとめ|”なんとなく”から抜け出すには。
理解できたら、自信を持って次に進もう
生成AIは難しいテクノロジーではなく、私たちの仕事や生活を助けてくれる便利なツールです。この記事で基本的な理解が深まったなら、ぜひ実際に使ってみてください。
- 完璧を求めず、まずは試してみる
- 使いながら「このAIの得意なこと・苦手なこと」を学んでいく
- 必ず人間の目で最終確認をする習慣をつける
生成AIは日々進化しています。「使いこなせるようになったら遅い」ということはなく、今からでも十分に活用の恩恵を受けることができます。不安や迷いがあっても、一歩踏み出してみることで、新しい可能性が広がるでしょう。
この記事は生成AIについての基本的な理解を深めることを目的としています。実際のサービスの利用規約や最新情報については、各サービスの公式サイトでご確認ください。
次に読む記事

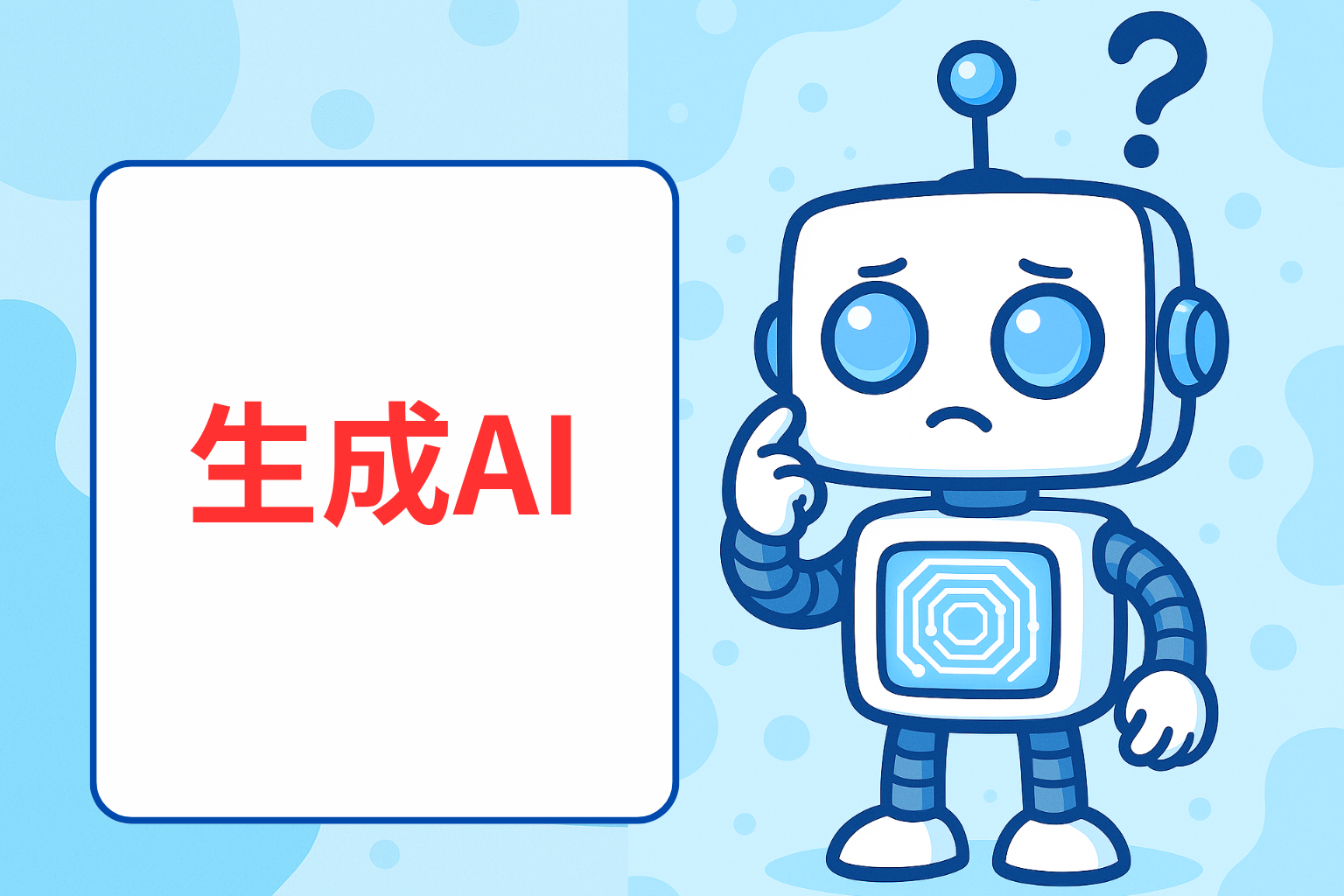


コメント